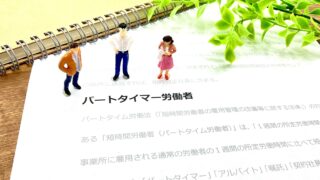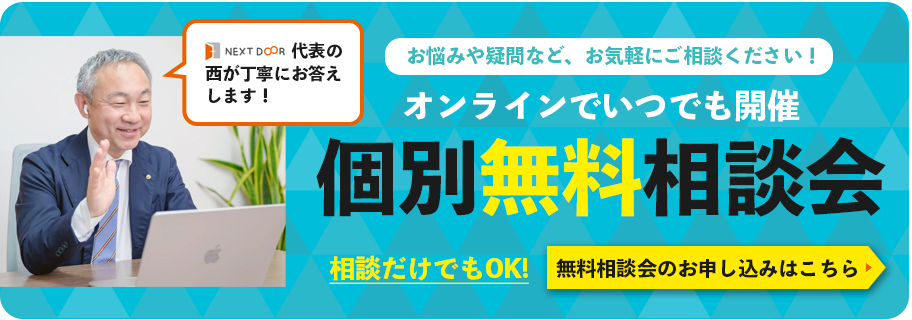外国人雇用でミャンマー人に特化した採用戦略で企業の成長を支援する特定技能外国人登録支援機関、ネクストドアです。
インバウンド観光の回復とともに、日本国内では外国人労働者の存在感がますます高まっています。
特に観光・接客業を中心に、言語や文化を理解する外国人スタッフが欠かせない存在となりつつあります。
しかし一方で、一部の観光客によるマナー違反が、外国人全体への誤解や偏見を生む原因にもなっている側面も。
本記事では、外国人労働者とインバウンドの関係性を整理しつつ、職場や地域で起こりがちな誤解、そして外国人が差別されないために企業が果たすべき役割について考えていきます。
外国人労働者とインバウンド観光の意外な接点とは?
昨今、日本国内で急増している訪日外国人観光客(インバウンド)。
都市部から地方まで観光地の活況が続く中、ホテルや飲食、交通、観光案内所などさまざまな業界で「多言語対応」と「文化理解」を担える人材へのニーズが高まっています。
その中心になっているのが、「外国人労働者」です。
まず、言語面での橋渡し役。
英語や中国語、韓国語を話せる外国人スタッフは、観光客にとって安心して利用できる環境を提供し、結果的にリピーターにもつながります。
たとえば英語だけではなく、よりニッチな言語(タイ語やベトナム語など)にも対応できるケースが増え、日本の“おもてなし”を支える重要な存在になっているのです。
さらに、文化面においても強みが。
自国の文化や慣習を知っている外国人労働者は、観光客が何を求めているか、何に驚き、何に不安を感じるかを“先読み”できます。
これにより、お客さまへの接触のタイミングや伝え方、笑顔の見せ方一つで満足度が上がるサービスが提供できるわけです。
これは、日本人スタッフだけでは気づきにくい視点ともいえるでしょう。
また、インバウンド客が多い地域ほど、多文化共生の実践現場にもなっており、地域活性化の一翼を担っています。
地元の祭りやイベントへ外国人労働者が参加する形で、地域住民と観光客、企業が交わる機会が増え、相互理解は深まっていくでしょう。
結果として、その地域自体のブランド価値が向上する好循環が生まれます。
一方で外国人労働者が果たす“人材育成”の役割も見逃せません。
社内の日本人従業員に対して、語学や異文化対応のノウハウを教えることで、企業全体の接客品質が底上げされます。
このように、外国人がいることが「社内教育の触媒」となり、組織のスキルアップにもつながる可能性が。
「外国人労働者×インバウンド」は、単なる労働力の補填ではなく、言語・文化・教育・地域促進と、多層的に企業と地域社会にメリットをもたらしているのです。
訪日客増加の追い風を受けて、この関係性は今後ますます強まっていくでしょう。
一部の観光客のマナー違反が外国人全体のイメージを左右?
一方で、近年、SNSやニュースなどで訪日観光客の「マナー違反」が注目を集めています。
例えば、公共の場での大声、ゴミのポイ捨て、文化財への無断接触など、日本人から見れば常識を欠いた行動も、異文化では悪意なく行われていることがあります。
しかし、こうした一部のインバウンド客による行動が、同じ外国人という枠組みで「外国人全体」への偏見につながってしまうケースがあるのです。
実際、まじめに働いている外国人労働者までもが「どうせ外国人だから…」といった先入観を持たれ、無意識のうちに距離を置かれたり、不当な扱いを受けたりする場面も少なくありません。
こうした状況は、外国人労働者のモチベーション低下や離職につながるばかりか、企業にとっても貴重な人材を失うリスクとなります。
特に観光地では、接客の最前線に立つ外国人スタッフが誤解の矢面に立たされることも。
たとえば、観光客への注意喚起を行った際、「あなたも同じ外国人でしょう」と冷たい目を向けられることがあり、精神的な負担も大きくなっています。
このような誤解を防ぐためには、企業側が積極的に「外国人労働者の役割」や「マナー違反との違い」を社内外に発信していくことが重要です。
例えば、店内掲示やウェブサイト、SNSなどを活用し、「私たちは国際的な職場です」「マナーを守る働き手がいます」というポジティブなメッセージを継続的に発信することが、社会全体の理解促進につながります。
また、地域社会との連携も大切です。
地域のイベントや清掃活動に外国人スタッフが参加することで、住民との距離が縮まり、「顔の見える関係性」が構築されます。
こうした草の根的な取り組みが、長期的には偏見を解消し、外国人労働者にとっても安心して働ける環境づくりにつながっていくでしょう。
外国人労働者が気づかずにしてしまいがちな“迷惑行動”とは?
とはいえ、日本人にとっての当たり前のマナーや文化も、外国人にとってはそうではない場合も多いもの。
外国人労働者でも、日本で働く際、知らず知らずのうちに“マナー違反”と受け取られてしまう行動をしてしまうこともあります。
これは本人に悪意があるわけではなく、多くの場合は文化や習慣の違いから来る「誤解」によるものです。
企業としては、こうした行動を未然に防ぎ、トラブルにならないようにすることが求められます。
よく見られるのが「声の大きさ」。
母国では普通のトーンで話しているつもりでも、日本人から見ると「うるさい」と感じられてしまうことがあります。
また、仕事中のリアクションがオーバーだったり、無意識に相手との距離が近すぎたりといった行動も、気をつけるべきポイントです。
次に、「時間に対する感覚」も大きく異なります。
日本では5分前行動が常識とされていますが、国によっては「時間は目安」という考え方が根強く残っています。
そのため、出勤時間や納期の遵守についても、明確な説明とルール設定が必要。
さらに、アイコンタクトやあいさつの仕方、メモを取る文化の有無など、細かな行動にも違いが現れます。
たとえば、目を合わせないのが礼儀とされる文化圏の人が、上司と目を合わせずに話すと「失礼だ」と誤解されてしまうことが。
このような“無意識のミス”を防ぐには、就労前のオリエンテーションや、日本でのビジネスマナー研修が非常に有効です。
また、日本人社員側にも「文化の違いによる行動かもしれない」という視点を持ってもらうことで、双方のストレスを軽減できるでしょう。
迷惑行動の多くは、誤解や情報不足から生じます。
事前に理解し、双方が歩み寄る姿勢を持つことで、職場のトラブルを最小限に抑えることが可能になります。
偏見や差別をなくすために企業ができること
外国人労働者が日本で安心して働くためには、受け入れる企業の姿勢が何より重要です。
特に、見えにくい偏見や差別を排除するには、組織全体で「多文化共生」の意識を共有し、制度と風土の両面から取り組みを進める必要があります。
まず、最も基本となるのが明確なルールづくりと説明。
就業規則や職場マナー、報告・連絡・相談の手順など、日本の企業文化を丁寧に伝えることが、誤解を防ぐ第一歩になります。
その際、なぜそのルールがあるのか、という背景まで説明することで、納得感を持って理解してもらいやすくなるでしょう。
次に、職場でのコミュニケーションを促進するための「交流の場」づくりも効果的です。
ランチ会や季節のイベント、異文化交流会など、気軽に会話できる機会があることで、外国人と日本人社員との間に信頼関係が築かれやすくなります。
特に、言葉の壁を越えた「顔の見える関係性」は、偏見をなくす大きな力に。
また、差別やトラブルが起きた際の「相談窓口」の設置も欠かせません。
外国人労働者が安心して声を上げられる体制を整えておくことで、問題の早期発見・対応が可能になります。
第三者によるカウンセリングや、母国語での対応も重要なポイントです。
企業の上層部が率先して「多様性を尊重する経営」を掲げ、行動に移すことも非常に大切。
多様な人材を活かす企業姿勢は、採用面だけでなく、ブランディングや顧客からの信頼にもつながっていきます。
今後、日本社会が少子高齢化と向き合う中で、外国人労働者の存在はますます不可欠になるでしょう。
そのとき「誰もが平等に働ける環境」を整えている企業こそが、持続可能な成長を実現できるのです。
まとめ
訪日観光客の増加に伴い、外国人労働者は多言語対応や異文化理解を担う存在として重要性を増しています。
一方で、一部観光客のマナー違反が外国人全体への偏見を生むことも。
外国人労働者が無意識にしてしまいがちな行動には文化的な背景があり、企業側の教育と理解が不可欠です。
差別や誤解を防ぐためには、明確なルール説明と相互理解の場づくりが重要。
企業の多文化共生への取り組みが、外国人と日本人双方が安心して働ける環境をつくる鍵となります。
登録支援機関である当社は、特定技能外国人の雇用はもちろん、外国人労働者全般に関するあらゆる知識や経験を持っています。
採用戦略のご相談や採用支援だけでなく、採用後の様々な注意点やアドバイス、支援実施のサポートも行います。
まずは「外国人採用戦略診断セッション」を受けてみて下さい。
60分無料のセッションで、貴社の状況をヒアリング。
貴社に合った外国人採用・育成戦略、支援計画やフォロー体制をご提案いたします。
疑問や不安のご相談だけでも、どうぞお気軽にお申し込みください。
投稿者プロフィール

-
9年以上にわたり、技能実習生から特定技能外国人までの支援に従事。
ミャンマーにおいて、特に技能実習生や特定技能外国人のサポートを継続的に行い、2ヶ月に一度ミャンマーを訪問して面接を実施。
特に介護、食品製造業へのミャンマー人労働者の就労支援で多数の実績。
日本語会話に特化したクラスの提供や、介護福祉士資格取得のためのeラーニングサポートを実施。
外国人雇用管理主任資格者
特定技能外国人等録支援機関19登-002160